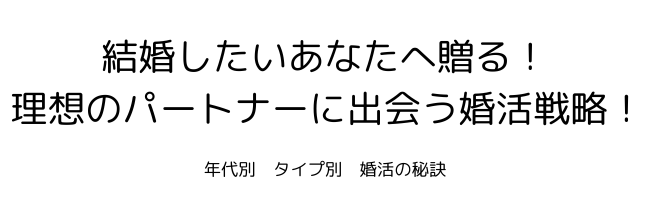第2話 ハイスペック男性と最初のデート 三橋翔太の場合
登録した婚活サイト「プレミアパートナー」は、ハイスペックな男女の出会いを支援する会員制サービスだ。入会は、男性は年収1000万円以上、女性は容姿審査の通過が必須条件。さらに、男性は医師や弁護士、経営者など、社会的地位の高い職業に就いている人が多い。女性も、容姿端麗なだけでなく、教養や知性、キャリアを兼ね備えた人が集まっている。
私は正直、これといった特技はない。囲碁はそれなりに強いが、プロフィールには無難に料理が趣味と書いてしまっている。でも、もしかしたら、女性の審査基準の方が甘いのかもしれない。仕事に関しては、地味だが長く勤めているし、応募写真もそこそこ美人に映っているものを使用した。結果、無事に登録ができたというわけだ。
【プレミアパートナーの特徴】
- 男性は収入1000万円以上のハイクラス層限定: 厳格な入会審査により、会員の質を高く保っている。
- 手厚いサポート: 専任コンシェルジュが、プロフィール作成からデートのセッティング、交際中の相談まで、きめ細やかなサポートを提供。
- 多彩な出会いの場: オンライン上でのマッチングだけでなく、会員限定のパーティーやイベントも定期的に開催。
- プライバシー保護: 個人情報の管理を徹底しており、安心して利用できる。
登録後、すぐに複数の男性から「いいね!」が届いた。その中で、最初にデートすることになったのが、外資系コンサルタントの三橋翔太さんだった。
待ち合わせ場所の丸の内へ向かう電車の中で、私は今さらのように不安になる。
「実際に会ったらがっかりされるんじゃないかな」
電車のガラス窓には、ごくごく平凡な女が映っている。身長158cmで、太っているわけではないが、モデル体型でもない。顔は童顔で、メイクをしても若く見られることが多い。
一方、三橋さんのプロフィール写真は、爽やかな笑顔が印象的だ。身長は182cmあるそうで、スラリとした体型。知的な雰囲気を醸し出す、切れ長の目に高い鼻。
元カレの拓也は、どちらかといえばガッチリ体型で、顔は濃い方だった。身長は170cmほどで、私がヒールを履いて並ぶと少し高いくらい。
……と、いけない。また思い出して、比べてしまっている。
待ち合わせ場所の高級フレンチレストランに着くと、すでに三橋さんが待っていた。グレーのスーツにネイビーのネクタイ、パリッとしたシャツ。洗練された雰囲気に、私の緊張はさらに高まった。
「権田さん、はじめまして。三橋です」
三橋さんは、写真通りの爽やかな笑顔で私に手を差し伸べた。
「はじめまして。権田桃子です。今日はありがとうございます」
私は、精一杯の笑顔で挨拶を返す。
食事をしながら、私たちは仕事の話や趣味の話をした。といっても、私はもっぱら聞き役に徹した。その方がウケがいいと、先日ネットで読み漁った婚活マニュアルに書いてあったのだ。

ちなみに今日着ているワンピースは、拓哉が前に薦めてくれたもの。我ながらどうかと思ったが、清楚で上品なワンピースは今日のデートにぴったりだから、割り切って着用することにした。
メイクもネイルもいつも以上に念入りに、ただしあくまでもナチュラルな雰囲気になるよう仕上げている。髪は全部おろし、毛先をゆるく巻いた。アクセサリーはゴールドのピアスだけだ。
三橋さんは、海外でのプロジェクト経験や、コンサルタントとしてのやりがいについて熱く語ってくれた。
途中までは、和やかな雰囲気だったと思う。彼は饒舌で、わたしが熱心に話を聞くので、気分が良さそうだった。しかし。
「権田さんは、食品メーカーの総務部で働いているんですね。総務って、会社の何でも屋さんみたいな感じですよね?」
私は驚いて、一瞬答えに窮した。総務の仕事は、決して楽な仕事ではない。会社を円滑に運営するために、様々な業務をこなしているのだ。
「……そうですね。社内の様々な業務をサポートしています」
冷静に、言葉を選んで返答する。
「残業とかあるんですか?最近は働き方改革で、定時で帰るよう促される会社も多いでしょう」
「繁忙期には、たまに残業もしますよ。まあ、大抵は定時で帰りますが」
「よかった」
「え?」
「仕事を頑張ってらっしゃる女性は尊敬しますが、僕は、基本的に女性はキャリアウーマンタイプよりも、桃子さんのような家庭的な方が好ましいと考えていて」
ちょっと待って。いつ、どんな流れで、私が家庭的な女だと思ったのだろう。料理が趣味と書いたから?それとも、男を立てるために、聞き役に徹していたから? ああそれとも、総務の仕事をしているから、仕事にこだわりがないと思われたんだろうか。
「私も、仕事は好きですよ。会社の中で、いろいろな部署の人と関わることができますし」
「やりがいとか感じてます?」
「……もちろん」
嘘だ。今の仕事も、進学する大学も、親の顔色を伺いながら決めたのだ。無難で、「生意気な」とか、「高望みだ」と言われないような選択をした。
本当はーーー本当は、私は、何をやりたかったんだろう?
「まあ、でも、無理することはないですよ」
三橋さんはまた訳知り顔で言った。彼は洗練された所作でカトラリーを動かし、高級ステーキを切っている。わたしは最初から、ぜんぜん味がしない。
「女性はやっぱり、家庭に入るのが一番幸せなんじゃないかなって、僕は思うんですよね。母もそうでしたし。父が日本橋で法律事務所を経営してるんですが、もう本当に忙しくて、家のことや子供のことは、全部母に任せきりだったんです。ただいまって学校から帰宅して、家の中に、こう、甘い焼き菓子の匂いが漂っていて。母がたまにケーキやクッキーを焼いてくれていたのが、すごく嬉しかったんですよね。だから僕も、妻には家庭に入ってほしいと思っています」
私は急激な喉の渇きを感じ、グラスに注いであったワインをぐっと一気に飲んでしまった。
三橋さんが、目を丸くしている。いけない。慌ててそばにあった水を一口、飲み直す。
「……すみません。喉が渇いて。間違ってお酒の方を飲んじゃいました」
苦しい言い訳だったのに、はは、と三橋さんは笑ってくれる。
「今日、外、すごく暑いですもんね。よかったらペリエとか注文します?」
「ありがとうございます……」
すぐに注文してくれる三橋さん。驚いただろうに、どこまでもスマートな振る舞いだ。
三橋さんの家は、都心の高級住宅街にある一軒家だと聞いている。一方、私の実家は、千葉の片田舎、築30年の古びたマンション。父は市役所勤務、母はパート勤務。私は幼い頃から、家計のことで両親が言い争う姿を何度も見てきた。
『誰のおかげで飯が食えてるんだ。養ってもらっている分際で、文句を言うな! おまえのようなバカな醜女をもらってやっただけでも、感謝してしかるべきだろう!』
酔っ払った父が、母に怒鳴りつけるのを、息を殺して聞いていた。母はそのたびに言いたいことを飲み込み、苦しそうにしていた。父に隠れて、こっそりと、台所の隅で泣いていた。
声も立てず。
物心着いたときには、わかっていた。父は典型的なモラハラ男だ。私は、絶対に父のような男とは結婚しない、生涯働き続ける女になる……そう、少女時代は考えていた。
父は、女の子に学歴は必要ない、という考えの持ち主だった。お金がもったいないと。それでも母が、私の大学進学を強く後押ししてくれた。お金も、十分な額の学資保険をちゃんと積み立てておいてくれていた。きっと、思うところがあったのだろう。
私は顔をあげて三橋さんをまっすぐに見る。
「私は、できれば仕事を続けたいと思っています。たとえ結婚し、子供ができても」
三橋さんは、じっと私の目を見つめた。
「……そうですか」
彼は、今度は落胆した顔を隠さなかった。
家に帰り、ベッドに横になりながら、三橋さんとのデートを振り返る。彼は、確かに魅力的な男性だが、価値観が自分とは合わないし、育った環境が違いすぎる。
私はもう一度、プレミアパートナーの規約を見直す。「お断りシステム」というものがある。その中でも便利そうなのが、「お気持ち確認機能」だ。
「お気持ち確認」機能
- メッセージのやり取りの中で、相手への興味が薄れた場合、「お気持ち確認」機能を利用することができます。
- この機能を使うと、相手に「もう少しやり取りを続けたいですか?」という質問が自動的に送信されます。
- 相手が「はい」と答えた場合は、引き続きメッセージのやり取りを続けることができます。
- 相手が「いいえ」と答えた場合、または24時間以内に返信がない場合は、自動的にマッチングが解除されます。
どうしようか悩んでいると、三橋さんの方から、「お気持ち確認」の質問が送られてきた。わたしは悩んだ末、「いいえ」を選択した。
少しもったいなかったかな。でも、三橋さんの方でも当然、違和感があったのだろう。
彼は私のプロフィールや写真、メッセージのやり取りから、私が控えめな良妻賢母タイプだと思ったのかもしれない。ハイスペックな男性と結婚し、専業主婦になりたがっていると。だから会ってくれた。
お気持ち確認機能を使用し、こちらに選択権を与えてくれたのは、彼ならではの誠実さかもしれない。
ぴったりの相手は、お互いに他にいる。そういうことだ。
「私は、私らしく生きたい」
わたしは天井を見つめながら、声に出して呟いた。
私は母のようにはなりたくないし、母が私を大学にやってくれた、その想いも無駄にしたくない。仕事は続けたい。その上でなお、できるだけ高収入な男性と知り合って結婚したいとも思う。なぜなら、継続して収入を得るということは、とても大変なことだ。高収入の男性は、努力をしてきた人が多いはずだし、眩しいほどの自信に満ち溢れている。
一方で、私はどうだろう。今のままの仕事でいいのだろうか。輝いていると言えるだろうか。
「私らしく生きる」ということは、もしかしたら、「裕福な暮らし」を諦めることにつながるかもしれない。
でも、まだ、始めたばかりだ。
ハイスペックでも、実家が裕福でも、価値観がぴったりと合う人が、きっとどこかにいるはず。
「まだ国枝さんと菅谷さんとのデートが残っている」
私は、冷蔵庫で冷やしておいたお酒を取り出す。ネットで取り寄せた福井の銘酒だ。それをコップになみなみと注ぎ、コンビニで買ったチルドの焼き鳥を温めた。
「美味し……」
今日食べたフレンチより、よほど美味しい。お酒は辛口が好きだし、そのへんの男より強い。そして好物は居酒屋のモツ鍋だ。そんなことを知られたら、婚活に差し障るだろうから、もうしばらくは内緒にしていよう。
ありのままの私でいたいと思いながら、まだ見栄をはろうとしている。
そんな自分に苦笑しつつ、押し入れから碁盤を引っ張り出した。拓哉が良い顔をしないから、長い間しまっていたのだ。囲碁は心を鎮め、戦略を立てるのに役立つ。
私は久しぶりに碁石の硬くて冷たい感触を確かめ、お酒をくいっとあおると、石を静かに打ち下ろした。
第3話に続く
この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事件などには一切関係ありません。